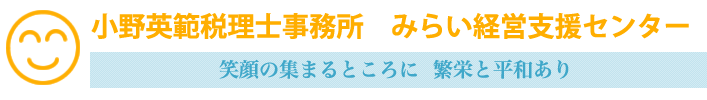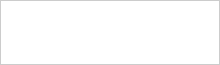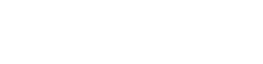令和のコメ騒動が長期化するのは生産力の低下も要因のようです。
今回の米価の急激な高騰は、2023年の猛暑による高温障害などがきっかけでした。
2018年にコメの生産量を調整する減反政策をやめた後も政府が「需給見通し」を作成し、主食用のコメから飼料用米や麦などに添削する農家に補助金を出していました。
実質的な減反政策を維持したため、わずかな供給量の減少でもコメ価格が高騰しやすくなってしまいました。
また、複雑な流通構造も原因のようです。
農林水産省によると、農業を主な仕事とする「基幹的農業従事者」は2015年の176万人から2024年には111万人に減少しました。
平均年齢はなんと69.2歳と高齢化も一段と進みました。
農業経営体数は2020年の108万から2030年には54万と半減することが予想されるそうです。
経営規模の拡大がない場合、2030年には2020年比で約3割の農地が利用されなくなる恐れがあると聞きます。
食料安全保障や地域社会維持の観点からも日本の農業は重大な岐路に立っています。
農業従事者が急速に減少する中、持続的な食糧供給と安定的な農業経営の実現という高いハードルが待ち構えています。
目先のコメ対策にとどまらず、農政の再構築ともうかる農業に向けた取り組みが急務ですね。
まずは1年でも永く米を作ることで美田を残していくことが、次の活路につながることを信じて、汗かきましょう。